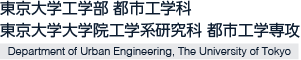- プロジェクト名: 下水道資源による地域循環の構築に関する研究
- 期間: 2021年~
- 共同研究機関: 公益社団法人 日本上下水道コンサルタント協会
概要
都市で発生した下水は処理場で処理されて綺麗な水になりますが、その際に一緒に発生するのが下水汚泥です。従来は廃棄物として焼却処分されていた下水汚泥ですが、農業において必要不可欠な栄養素である窒素やリンが豊富に含まれていることから農業分野への有効利用に注目が集まっています。下水汚泥を微生物の力で発酵させることで作られる下水汚泥肥料は、全量を輸入に依存している化学肥料の利用を減らしながら美味しい野菜や果物を生産することができ、さらにバイオマス利用として温室効果ガスの排出削減にもつながる、環境にやさしい取り組みです。
しかし下水由来というイメージの悪さもあってか汚泥肥料の普及は進んでおらず、肥料を作っても売れ残ってしまう懸念から自治体も取り組みにくい現状があります。このような状況において本研究は汚泥肥料の普及拡大を目指し、汚泥肥料を販売する事業者や利用者である実際の農業従事者の声を聞きながら、経営学のイノベーション理論等を活用した効果的なアプローチの方法や普及プロセスを研究しています。
プロジェクトが目指すもの
本研究による汚泥肥料の普及方策によって下水汚泥肥料への需要が高まり、現在焼却している下水汚泥を肥料化する取り組みが全国的に進むことを目標としています。下水由来の汚泥肥料が地域で活用されるようになれば地域内で資源が循環し、経済的にも良い影響を及ぼすと考えられます。さらに、国外からの輸入に全量を依存している化学肥料の利用割合を削減することで食糧安全保障や温室効果ガス削減、安価な農作物の供給が可能になります。

調査内容と成果
下水汚泥肥料利用の先進事例である佐賀県佐賀市や現在利用が進んでいる長野県富士見町、汚泥肥料の製造企業や自治体などで現地調査を行っています。汚泥肥料の普及に効果的な情報伝達の方法や汚泥肥料の利用可能性が高い農家の属性、農家が汚泥肥料に対して抱く印象・懸念点などについてインタビューし、アンケート調査によってこれらの裏付けを行いました(富士見町では田植えにも参加)。



調査の結果、地域内に精神的支柱となるリーダーがいると普及が進みやすいこと、農業収入割合が低い(農業以外からの収入が多い)農家ほど下水汚泥肥料への利用意志が高いこと、安全性に対して懸念を抱く農家が多いが情報公開や信頼される者の説明により安心感が高まることなどがわかり、これらをもとに下水汚泥肥料普及の理想的なプロセスモデルを構築しました。
「普及」に着目した本研究の独自性とその成果は、工学だけでなく、農業関係の研究機関や全国の自治体、水及び農業に関係する産業界からも注目されています。